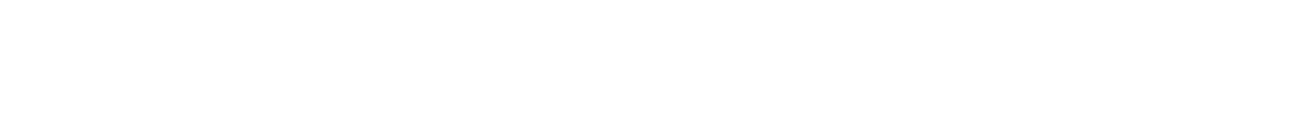かの日のユートピア
麗しの園よ、そが流れ甘く冷し
樹には歌う小鳥の調べ妙に。
眼も彩にチューリップ咲きむれ
くさぐさの果實樹に滿つ。
そよ風は渡る綠の木陰
美しきじゅうたんもて敷きなせるか、麗しの園。
サアディー『ゴレスターン』,1258
【第一日】
主は光を創造し、光と闇を分ける

月曜日。天気、不明。時間も、よくわからない。
まだ眠りの中にいたはずの私は、気づけばXXXXに腕を引かれていた。手短におはようと告げられ、返事もそこそこに寝ぼけたままの私と彼のお気に入りがたっぷり詰め込まれたトランクは大きな車にぎゅっと押し込まれた。エンジンが唸りを上げ、もう下車が許されないことを告げる。どうしたものかと思いながらぼうっとした頭で隣の席を見遣れば、鼻歌混じりの上機嫌な彼が私に微笑みかける。
「まだ寝ていてもいいよ」
ワシャワシャと頭を撫でる手にすっかり安心感を覚えてしまうのは、昔の習慣から身についたものだった。彼に連れられる場所ならまぁどこだっていいか、と思いながらまた微睡み、再び意識は夢の中に落ちていった。
後から考えてみれば、こんな強引なやり方は珍しいように思う。いや、懐かしいと言った方が適切かもしれない。近頃の彼は私の意志を何より尊重するが、私が何も知らぬ子どもであった時は多少強引にでも様々なところに連れ出して、目に留まったものひとつひとつの名を教えてくれた。そこで初めて、私はこの世のおよそ全てのものには名前があることを知った。これはリンゴだよ、と言って果物籠の中から手渡された赤い姿を見て初めて、これが『リンゴ』で、そのほかの橙色の楕円球や黒っぽい小さな球体が連なったものが『リンゴ』では無いことを知った。名前をつけて分けることで、初めて世界をわかることが出来たのだ。私に限らず、この世界に生まれ落ちた子らは皆そのような過程を経て言葉を知り、世界を知覚する。それくらい、言葉は重要だ。神様だって「光あれ」と、言葉で世界を創ったのだから。神が光と闇を分けたことで世界に昼と夜が生まれ、そこから時間という秩序が生まれた。私がXXXXに言葉を教わって初めてこの世界を知ったのと同じように、何にも名前がなく何もかもが不可分であった混沌の世は、神によって名付けられ分けられることで秩序を得たのだ。
さて、しばらくすると、香ばしくほの甘い香りに鼻腔を擽られて目が覚めた。目を開けば車内に備え付けられた小さなテーブルの上にボーンチャイナ製のマグカップがあり、中にはたっぷりとミルクを加えられたイングリッシュ・ブレックファスト。どうやら朝食は車内で頂くらしい。
XXXXは私が目覚めたことに気づくと、お気に入りのパン屋の紙袋からサンドウィッチを取り分けながらこの度の誘拐事件のいきさつを話し始めた。
どうやらこの車の行先は彼が最近譲り受けたカントリー・ハウスらしい。長く使われておらず随分と荒れているから、その整備を私にも手伝って欲しいのだそうだ。とは言ってもほとんどのことは業者に任せるようなので、正しくは見張り役中の退屈しのぎに付き合えということだろう。「ついでに、ぼくも君も1週間ほど休みを貰ったから」と軽く告げられた時にはさすがに少し驚いた。閑散期で元より休みの多い週であったとはいえ、つい脳裏には眉間に皺を寄せるXXXXの顔が浮かぶ。お土産くらいは持ち帰った方が良いかもしれない。
おしゃべりをしているうちに、果たしてどれほどの時間が経っただろうか。ごく静かなブレーキ音と共にはたらいた慣性力によって会話が遮られ、私たちと外界を隔てていた重たいドアがゆっくりと開く。
「さあ到着!ここがぼくたちの新世界だね!」
朗々とした声に導かれるようにして眩しい陽光が車内に飛び込んだ。
ああ、もうすっかりお昼だったんだ。
【第二日】
主はおおぞらを創造し、水と水とをその上下に分ける

火曜日。天気、曇り。湿気の多い朝のダイニング。
二人で過ごすには随分と広いカントリー・ハウスの中で数少ない整備された空間が、このダイニングと昨晩利用した寝室のふたつだった。十分に生活ができるだけの設備を整えた上で招いてくれたことに感謝しなければと思うくらいに、この屋敷は混沌としていた。
昨日初めて見たカントリー・ハウスの外観はすっかり蔦や大きな樹木に覆われてしまい、隙間から僅かに灰色のコッツウォルズ・ストーンが覗くばかりだった。それどころか、その樹木たちは屋敷周りの空をすっかり覆ってしまっていた。このじめじめとした空気は気候のせいだけではないらしい。
「まあこの湿気とも、今日のうちにおさらばできるはずだから」
たっぷりと湿気を含んで膨らんだ私の髪を戯れに梳かしながら、XXXXはそう言った。今日のうちに伸びに伸びた樹木などをおよそ間引いてやるそうだ。そして私は鼻歌交じりに髪を弄るXXXXに身を委ねながら、昨夜床に就く頃に彼がぽつりと呟いた言葉を思い出す。
『XXXX。こんな屋敷だけれど、ぼくはね、この屋敷を結構気に入ってしまったの。家族みたいに大好きな君を招くくらいにはね』
訊いたところによると、この屋敷はどこかの好事家がわざわざ外国から移築してきたものだそうだ。しかしそれにも関わらず、すっかり忘れ去られていたところを彼の実家が買い取ったらしい。忘れ去られて、ろくに手入れもされないままに薄汚れてしまった。けれど、そんな姿でも彼の目には何か光るものが映ったようだ。例えばそれは僅かに覗く壁面の凛々しさかもしれないし、草木に呑まれても尚静謐さを失わない居住まいかもしれない。泥まみれになりながら懸命に生き延びようとした子犬を拾ったときも、きっと彼は同じようにその子犬にピンとくるものがあったのだろう。
私が窓の外を覗いたり時折業者に指示を出しに出向くXXXXの姿を眺めたりしてのんびりと過ごしているうちに、外の澱んだ空との境を曖昧にするほど鬱蒼と繁っていた木々はみるみると間引かれ、景色が明らむと同時に空が開けていった。都会の狭い青空に見慣れてしまった私たちにとって、それは広い広い空だった。
予報によれば明日の天気は晴れ。その予兆が雲の切れ間からこっそりと顔を覗かせ、光の筋が地上に降り注いでいた。
【第三日】
主は下の水をひとところに集め、陸と海を分ける

水曜日。天気、予報通り晴れ。木々の瑞々しい香りが漂う真昼の森林。
屋敷内に清掃が入るために、その間は外で過ごそうということになった。すっかり綺麗に整えられた屋外を二人で見てまわれば、陽光に照らされた緑の葉がキラキラと輝いているのが目に入る。
「ほら、ここ。よく見て。川と池の跡があるんだけれど」
数名の作業員が集まったあたりに目を遣ると、確かに川とは呼べない程の湿気た窪みがある。
「せっかくだから、ちゃんと水が流れるようにしてもらおうと思ってね」
かなり大掛かりな作業になるから、こちらもやはり数日かかりそうだ。けれど、日当たりのすっかり良くなったこの場所に川面の輝きが加われば、それは大層良い景色だろう。
「さて、これさえ終わってしまえば大枠は完成だから、あとは何を詰め込んでいくかだね」
「なにか、目星はつけているの?」
そう問えば、少し唸った後にXXXXは答えた。
「とにかく、ぼくが美しいと思えるもの!」
パッと顔を輝かせながら言うなり、XXXXは駆け足で屋敷に戻り、あれよこれよと様々に手配を始めた。明日からはさっそくこの屋敷中に彼が美しいと思えるものを詰め込んでいくようだ。
いつだったか彼はXXXXに、単なる荷物持ちでもできるだけ愛すべきもの、美しいものを選びたいのだと言っていたっけ。泥まみれの子犬を拾った時も、可哀想だったからなどという慈愛の精神があったことを否定こそしないけれど、それだけでは決してない。彼の美学に適うものだからこそ、彼は捨て置かずに拾い集め、そして一度拾ったからにはその美しさを認め続ける限り愛を込めて磨き続けるんだ。そう生きることで、彼は彼自身を愛せるから。彼自身の、魂の高潔を守り抜けるから。
そうして愛せる自分であるために沢山のものを拾い集め磨き上げ出来た彼の、おそらく最初の拾い物が他でもない私であったのだとすれば……それを私は心より喜ばしく、そして誇らしく思う。
【第四日】
主は草や果樹を創造し、地に生えさせる

木曜日。天気、晴れ。森林の中の、少し開けた草原。
「美しいと思えるもの」とやらのまず1つ目は、これからここに造られる小さなフラワーガーデンだった。二本の果樹を中心に、手前には白いアイアン造りのパーゴラが、奥の方には元から備えてあったのであろう石造りのガゼボが既に配置されている。ガゼボは移築時からあったものなのか相当古そうだったけれど綺麗に掃除されていたので、今日はそこから造園の様子を見ようということになった。
青々と広がった草原はみるみるうちにレンガや砂利で区分けされ、色や香りごとに仕分けられた花の苗が植えられていく。こっちは白、向こうは赤――。
「バラは花の女王様だから、いっそう丁重に扱わなきゃね」
ガゼボのそばに置かれていたまだ蕾のままの苗を愛しげに眺めながらXXXXは言った。
「私も何か植えてみたいな」
「じゃあ、このバラの苗はぼくらで植えようか」
そう言って立ち上がると、苗木のそばに向かった。蕾は小さいけれど、その内側に秘めたエネルギーがはち切れそうなほど生命力に満ち溢れていた。この辺りに植えようかと触れた土は少し冷たくて、固い。シャベルを片手に二人で少しずつ解しながら腐葉土を混ぜ、まあるい穴を掘ってから苗を植えた。私たちが植えたバラの苗木は小さいけれど、どんな花よりも凛とした居住まいをみせていた。
「もうすぐ咲くかな」
「帰る頃にはきっと咲き始めるだろうね」
辺りを埋め尽くすたくさんの蕾は今か今かと咲き誇る日を待ち望んでいる。その先を見渡してみれば、西の空が朱い。帰る頃には、か。この休暇も折り返しだ。
「手、洗おうか」
土で汚れた手と手を繋ぎあって、私たちは舗装された砂利道をゆっくりと歩き出した。
【第五日】
主は空と海の生き物を創造し、その繁栄を祝福する

金曜日。天気:やや曇り。川のせせらぎを聴きながら。
先日見かけた際には湿地ほどに過ぎなかった窪みは、いつのまにか立派な川として仕上がっていた。
「おや」
耳をそばだてると、微かに生き物の鳴き声が聞こえる。導かれるようにして川辺に歩み寄ると、小さな鳥があたりに転がった木の切れっ端を集めていた。
「どうしたの、XXXX?」
「ほら、これ」
シーッと指を立てて合図すれば、XXXXは足音を潜めてそっとこちらに近づいてきた。
「おや、かわいらしいね」
小鳥に気づかれないよう少し離れたところから観察していると、そのうち小鳥はパタパタと羽ばたき、そして近くの木の太い枝へ降り立った。よく見ればその辺には、作りかけの巣が見える。
「こんなふうに小さな動物たちが集まるのも悪くないね。屋敷の裏小屋に巣箱があったから、いくつか架けてみようか」
鳥たちの囀りが満ちた自然のほうが、彼にとっては愛しいのだろう。私たちは早速小屋から小さな巣箱を持ち出すと、屋敷内の木々にそれを取り付けた。作りかけの小鳥の巣を邪魔しないように、慎重に。
彼はこうした些細な出会いですら、愛せてしまう。花も、動物も、人だって。だからXXXXは、アイドルに向いているのだと思う。かつて私にうさぎの世話をするように言った彼は、きっと私にもそうなることを期待していたのだろう。
そんな彼のおかげで、今では私も人間を含め生き物は興味深いと思うけれど、それは彼らが未知数だから。知り尽くすことができないから。そんな知的好奇心が原動力であり、これが愛といえるかはよくわからない。彼の在り方と私の在り方のどちらが良いだとか悪いだとか、そういうものではないだろうけれど、私には得がたい感覚をもつ彼はどこか眩しい。
地面と木の上を往復しながら巣作りに勤しむ小鳥を眺めながら、目を細める。彼が愛する世界を私も愛せるよう、せめて祈ろうか。
生めよ、ふえよ。水に満ち、地に満ちよ。
【第六日】
主は空と海の生き物を創造し、その繁栄を祝福する

土曜日。天気:やや曇り。川のせせらぎを聴きながら。
先日見かけた際には湿地ほどに過ぎなかった窪みは、いつのまにか立派な川として仕上がっていた。
「おや」
耳をそばだてると、微かに生き物の鳴き声が聞こえる。導かれるようにして川辺に歩み寄ると、小さな鳥があたりに転がった木の切れっ端を集めていた。
「どうしたの、XXXX?」
「ほら、これ」
シーッと指を立てて合図すれば、XXXXは足音を潜めてそっとこちらに近づいてきた。
「おや、かわいらしいね」
小鳥に気づかれないよう少し離れたところから観察していると、そのうち小鳥はパタパタと羽ばたき、そして近くの木の太い枝へ降り立った。よく見ればその辺には、作りかけの巣が見える。
「こんなふうに小さな動物たちが集まるのも悪くないね。屋敷の裏小屋に巣箱があったから、いくつか架けてみようか」
鳥たちの囀りが満ちた自然のほうが、彼にとっては愛しいのだろう。私たちは早速小屋から小さな巣箱を持ち出すと、屋敷内の木々にそれを取り付けた。作りかけの小鳥の巣を邪魔しないように、慎重に。
彼はこうした些細な出会いですら、愛せてしまう。花も、動物も、人だって。だからXXXXは、アイドルに向いているのだと思う。かつて私にうさぎの世話をするように言った彼は、きっと私にもそうなることを期待していたのだろう。
そんな彼のおかげで、今では私も人間を含め生き物は興味深いと思うけれど、それは彼らが未知数だから。知り尽くすことができないから。そんな知的好奇心が原動力であり、これが愛といえるかはよくわからない。彼の在り方と私の在り方のどちらが良いだとか悪いだとか、そういうものではないだろうけれど、私には得がたい感覚をもつ彼はどこか眩しい。
地面と木の上を往復しながら巣作りに勤しむ小鳥を眺めながら、目を細める。彼が愛する世界を私も愛せるよう、せめて祈ろうか。
生めよ、ふえよ。水に満ち、地に満ちよ。
【第七日】
主は全ての作業を終え、安息する

日曜日。天気:晴れ。あたたかい日差しが射し込む寝室。
一週間分の夜を過ごした大きなベッドは私たち二人が眠るにも十分で、出会ったばかりの頃を思い出す。XXXXはその名が体をあらわすのか、陽だまりのようにあたたかい。一晩同じ布団の中で過ごせばすっかりおんなじ体温に温められてしまって、そうして分け与えられた温もりこそが愛なのだろうと知る。
「XXXX、おはよう」
眠たげな身体をゆったりと動かしてこちらに向き直ると、彼は微笑んでそう言った。そのまま両腕を大きく開き、幼い頃と同じように私をぎゅっと抱きしめる。あたたかい。
「あたたかいね」
「うん、どこまでが私かわからなくなってしまいそう」
「それは困るね。別々じゃないとこうやって抱きしめられないもの」
仮にひとつになることが出来ればそんな手間もないんじゃあないかな、などと私は思ってしまうけれど、そんな返答はあまり彼好みでは無さそうだ。いかにも人間の営みらしい、手間ひまかけたものが愛しいのだろう。
温もりに後ろ髪を引かれながらも二人でシーツから抜け出し、朝食や簡単な身支度を済ませてから改めてこの屋敷を見て回ることにした。
森を歩けば瑞々しい風が肌を撫でる。川辺を歩けばどこから訪れたのか小魚や小鳥たちが賑やかに過ごしている。蔦に覆われたパーゴラをくぐれば、ささやかに咲き始めた花々が私たちを歓迎する。
「これ、お土産にしちゃおうか」
そう言ってXXXXが指さしたのは、二人で植えたバラの苗木の、今にも開きそうな赤い蕾だった。
「帰ったら事務所にでも生けておこうね」
パチン、と小さな音が鳴って花のついた枝がひとつ、切り離された。私も真似てもう一本切り取る。軽く触れた棘が肌を擦り、ほんのわずかな痛みが走る。
「この花、どれくらい保つかな」
「まあせいぜい、五、六日といったところだね」
そう聞くと、ほんの少し惜しいようにも思える。切り離してしまったことでこの花の命は多少なりとも短くなってしまったのではないだろうか。
「少しくらい、申し訳ないことをしたような気持ちになるべきなのかな」
「そんな必要はないと思うけれどね」
案外とあっさりXXXXは答えた。
「だって、この花にとっての幸せなんて誰にもわからないからね。だからぼくはそんな考えてもわかりっこないことのためには動かない。ぼく自身やぼくの周りの人がこの花を見て心慰められるなら、それがぼくにとって幸せだから。そんなぼく自身の幸せのためにこの花を摘むね」
「……そっか」
XXXXらしいな、と思った。客観的に見た正しさなんて、きっと彼の中には存在しない。自分自身や、自分の愛するものたちが幸せだと思えることこそ彼にとっては正しいのだ。
「さぁ、そろそろ帰ろうね!」
「そうだね。こんな休暇もたまには楽しいけれど、今はまだ休む時じゃない」
「うん。おじいちゃんになって体が動かなくなったらいやでも毎日がお休みになっちゃうんだから……それまではせめてぼくの、ぼくたちの幸せのために 働こうね」
すっかり整ったこのカントリー・ハウスは快適だ。恵みに満ちた、何ひとつ不自由のない楽園。けれど片田舎のほんの一画だけじゃあ、いつの間にか欲深くなってしまった私たちには……知恵を得てしまった私たちには、少し物足りない。
帰ったら、今度はこの世界ごと楽園にできるよう努めよう。私たちの幸福のために、正しさのために、そしてなによりも、愛のために。